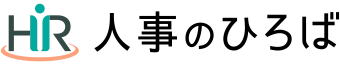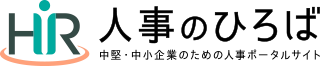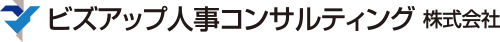本コラムでは、昨今、人事制度のトレンドとして注目されているキーワードの一つである、ジョブ型人事制度を取り上げます。
主に中堅・中小企業を対象として、ジョブ型人事制度を導入する際のポイントについて解説いたします。
中堅中小企業におけるジョブ型人事制度の考え方
(1)ジョブ型人事制度とは何か(メンバーシップ型人事制度との違い)
ジョブ型人事制度とは、従業員の職務内容を明確に定義した職務定義書を作成し、その職務に必要なスキルや成果に基づいて評価・報酬を決定する人事制度です。日本企業で多く見られるメンバーシップ型人事制度が、雇用の安定性や職務範囲の柔軟性を重視するのに対し、ジョブ型は個々の職務と成果を重視します。
メンバーシップ型では、年功序列や長期的な雇用関係の中で従業員の貢献を評価するのが一般的です。一方ジョブ型は、具体的な職務や役割を基準に報酬やキャリアパスを設計するため、透明性のある処遇を実現できます。
(2)ジョブ型人事制度の導入は企業が抱える人事上の課題解決に貢献する
ジョブ型人事制度を導入することで、昨今企業が抱える様々な課題(下記①~④のような事例)を解決できると言われています。
①上昇を続ける総額人件費(平均年齢の上昇と相関)への対応
ジョブ型人事制度では、職務内容や責任範囲に基づいて報酬が決定されるため、年齢や勤続年数に影響されない報酬体系を構築できます。
②成果と報酬のアンバランス(ベテラン・シニア社員)の是正
業務遂行能力が低下した場合には、役割の見直しや職務変更を実施することで、成果と報酬の適正化を図ります。そのため、成果が上げられていないベテランやシニア社員が、年功的要素によって高い給与を得ているという不公平な状況を解消できます。
③高度専門人材確保の困難性への対応
職務内容や必要なスキルを明確にし、職務に基づいた透明化された報酬体系や入社後のキャリアパスを提示することで、高度専門人材の採用競争における優位性を確保できます。
④グローバル人事への対応(国際企業のみ)
ジョブ型人事制度は、国際的に広く採用されている仕組みであり、職務基準に基づく人事評価や報酬制度は世界各国で適用可能です。これにより、海外拠点や文化の異なる従業員であっても、一貫性のある制度で処遇することができます。
一方で、各国の労働市場や法規制に柔軟に対応できる仕組みであるため、地域の市場特性を反映した報酬設定や評価基準を取り入れることも容易です。 結果として、グローバルなタレントマネジメントが実現しやすくなります。
(3)中堅中小企業を対象としたジョブ型人事制度とは
前項で、ジョブ型人事制度を導入することによる、企業が抱える人事の課題解決について述べました。しかし、職務記述書の内容に基づき、職種と職務を特定して報酬と対応させる、完全なジョブ型人事制度を採用して効果を得られるのは、人材が豊富である大企業に限定されがちです。
中堅・中小企業でジョブ型人事制度の導入を検討する際は、制度のメリット・デメリットを把握し、自社の状況を考えて効果が期待できる点を取り入れるといった、柔軟な対応が必要になります。
①メリット
・人件費の適正化:職務に対する報酬となるため年功的要素がなくなり、人件費を適正化できる。
・適所適材の人材配置:ポジションの役割を明確にした上で、外部からの登用も視野に入れながら最適な人材を配置できる。
・評価の透明性向上:職務に基づく評価が可能となり、属人的な判断を排除できる。
・キャリア形成支援:従業員が自身の職務やスキルに基づいたキャリアパスを描きやすい。
②デメリット
・初期コストの増加:職務分析や評価基準の策定に多くの時間とリソースが必要。
・柔軟性の低下:職務を厳密に定義しすぎると、急な業務変更への対応が難しくなる。
・人材流出のリスク:スキルを基準に評価されることで、従業員の市場価値が向上し、他社への流出リスクが高まる。
中堅・中小企業では、大企業ほど人材が豊富ではないため、デメリットにもある通り職務内容を厳密に定義し過ぎてしまうと、急に人員が必要となった業務に、既存の従業員を割り当てることが難しくなるといったことが懸念されます。
一方で、年功的要素を除いた職務内容に対応した報酬体系を取り入れて、人件費を適正化できることは、中堅・中小企業にとって非常に魅力的であるといえます。 次章では、中堅・中小企業がジョブ型人事制度を導入する際のポイントを解説します。
中堅中小企業向けのジョブ型人事制度導入のポイント
(1)職務や役割を基準とする等級制度の整備・見直し
等級制度は、人事制度の骨格にあたる部分です。中堅・中小企業の良さでもある人事の柔軟性を活かしながら、ジョブ型人事制度のメリットを取り入れた等級制度を設計することが重要になります。設計のポイントは下記の通りです。
・経営戦略、今後の事業展開、人事的課題などから、「必要な人材」「あるべき組織」「その組織に必要な役職」について検討し、
それぞれの定義を基に等級制度を設計する。
・完全な職務等級でなく、非管理職層は職務中心に、管理職層は役割中心で組み立てる。
・メンテナンスコストが膨大になる職務記述書は作成せず、階層別の役割の内容など、等級定義をしっかりと作る。
・多様な人材が活躍できるよう、総合職、専門職、職務限定職、地域限定職の複線型人事制度を検討する。
(2)「仕事給」を中心とする賃金制度
ジョブ型人事制度では、職務に基づいて報酬を設定する「仕事給」の考え方を取り入れ、生活保障や年功的な要素を、報酬体系から少なくしていくことが重要になります。具体的なジョブ型の考えに基づく賃金設計(先述した等級制度の内容とも連動)のポイントは下記の通りです。
・年齢給、職能給(勤続年数と能力の向上が相関する前提で賃金が上がる)は廃止し、基本給を一本化する。
ただし、新卒からの若年層には、一定の定期昇給の要素を残す。
・階層別、職種別の賃金相場を調査・把握したうえで、月例給、賞与、年収の水準を再設定する。
そのために、各賃金設定で算定するモデル賃金を緻密に作成し、等級ごとの想定賃金と、世間相場の水準を比較する。
・職種別賃金体系の導入も視野に入れる。
・職務関連手当(役職手当など)は手厚く、生活保障手当(家族手当、住宅手当など)は少なくする。
・基本給(賃金)表は、等級ごとの下限・上限金額を設定する範囲職務給の考え方を取り入れる。
賃金の範囲が、等級に求められる役割の大きさを表す。
・昇給、賞与の評価格差を明確にし、上位評価者に対する人件費の割振りを大きくする。
(3)等級制度と連動して評価の軸を定める評価制度
人事評価制度は、担当する職務、担当する役割に応じて、成果(結果)、行動(価値観)、能力の組み合わせで検討していきます。具体的な内容は下記の通りです。
・等級(階層)別、職種別に会社が社員に期待することを明確にする。
・中期的な視点から設定された成果責任に基づく目標管理制度(MBO)を重視する。
・成果を創出するための行動基準(発揮能力)を示す。また、必要に応じて価値観やマインド、経営理念の実践に関連する要素も盛り込む。
まとめ
中堅・中小企業がジョブ型人事制度を導入することで、社員のスキルを最大限に活用し、競争力を強化できる可能性があります。しかし、制度導入にはコストや負担も伴うため、目的を明確にし、現場の状況に合った柔軟な運用を心がけることが成功の鍵となります。
特に職務や評価制度、賃金体系の整備は、企業全体の戦略と密接に関連するため、計画的に進める必要があります。社員と経営陣が一体となり、継続的に改善を図ることで、ジョブ型人事制度は組織の成長に貢献する有効なツールとなるでしょう。