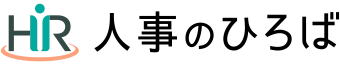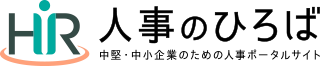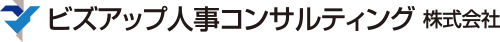シニア人材活用の重要性
日本社会では急速な高齢化が進み、労働人口の減少が深刻な課題となっています。内閣府の『令和5年版高齢社会白書』によると、日本の高齢化率(総人口に占める65歳以上の割合)は令和4年10月1日現在で29.0%に達しており、2036年には33.3%に上昇すると予測されています。つまり、約3人に1人が65歳以上となります。
一方で、若年層の労働力人口は減少の一途をたどっており、現状の年齢構成のままで企業が必要な労働力を維持することは極めて困難です。
このような状況を踏まえると、企業は60歳以上のシニア社員の活用をより真剣に検討する必要があります。特に、専門性を要する業種では、長年の経験を持つシニア社員のノウハウ・技能の維持・継承は不可欠であり、より積極的な活用が求められます。
法改正の影響もあり、厚生労働省の『令和5年高年齢者の雇用状況』によれば、60歳定年企業での希望者の継続雇用率はほぼ100%に達しています。
しかし、70歳までの高年齢者就業確保措置を実施している企業は29.7%です。この低い導入率の背景には、多くの問題が関係しています。例えば、65歳以上のシニア社員を活用するためのそもそもの職務選択肢の幅、処遇再設定の手間、総額人件費の増加、シニア社員の活用のための個別の職場環境整備の難しさなど様々な問題が企業別に存在します。また、問題に対処する際には、改正パートタイム・有期雇用労働法による「同一労働同一賃金」の原則に基づく法対応を考慮することも必要です。
このようにやや複雑な対応を求められますが、シニア社員の活用を単なる「雇用年齢の延長」ではなく、「中長期の成長戦略の一環」として捉え、着実に取り組んでいただくことをお勧めします。このテーマは前述の通り、労働力の確保のために中長期で重要な検討事項であることは明白です。さらに、シニア人材のノウハウ・技能の保存・伝承は、企業の競争力を維持・向上させることにもつながるため、「中長期戦略の一環」といえるのです。例えば、シニア人材の長年培われたノウハウ・技能は、企業内固有の財産であることが多く、そのノウハウを失った場合には今までと同じようにビジネスを進めることは不可能です。逆に適切にノウハウを継承できた場合には、維持だけでなく若い世代による更なる発展も期待できます。
また別の視点として年金制度の持続可能性が問われる中、シニア社員を継続的に雇用可能な環境を確保することは、社員全体に長期的キャリアや生活の安定・安心感を与えることも可能となるでしょう。 以上の通り企業は中長期の成長戦略の一環として、各社の事業戦略に合わせたシニア人材の活用方針を真剣に考える重要性が増しています。
シニア人材活用に関する法整備の変化
2021年4月に施行された改正高年齢者雇用安定法により、企業には70歳までの雇用確保措置を講じることが努力義務として求められるようになりました。これにより、企業には以下のいずれかの措置を講じる努力が求められています。
改正のポイント ~70歳までの就業機会の確保(努力義務)~
65歳までの雇用確保(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務を新設。(令和3年4月1日施行)
- 70歳までの定年引き上げ
- 定年制の廃止
- 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む) - 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
- 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
※厚生労働省「高年齢者雇用安定法改正の概要」
現状は「70歳までの就業機会の確保等の措置」は努力義務ではあります。しかし、中長期的には罰則規定ありの義務化することも見越し、今のうちに対応の方向性を見定めることは有用です。すでに大手企業では、70歳までの雇用延長を進める動きが見られています。一方で中小企業ではまだ対応を決めかねることが多いのも実情です。
ただし、この中で外してはならないのは、高年齢者雇用安定法に基づく「希望者全員への65歳までの雇用確保の完全義務化」です。中小企業でも確実に、2025年4月1日以降対応していないと法違反となります。 今後の社会環境の変化に伴い、シニア社員の雇用に関する法規制はさらに厳しくなる可能性があります。そのため、短期的には65歳までの雇用確保への確実な対応を行い、中長期的には70歳までの就業機会確保に向けた体制整備を段階的に進めることが中小企業にも求められています。こうした準備を進めることで、急な法改正変更にも柔軟に対応できるだけでなく、安定した人材確保・中長期戦略の実行にもつながるでしょう。
シニア社員を有効活用するための人事施策の考え方
今後の動向を踏まえたシニア社員に対する人事施策は、主に「シニア社員に担わせる役割・職務の見直し」と、「対応する処遇設計の最適化」、「役割別の柔軟な働き方の導入」の3つをまず検討することをお勧めします。その設計過程では、前述の通り単なる雇用延長ではなく、企業と社員双方にとって持続可能な仕組みを構築することが重要です。
1つ目の「シニア社員に担わせる役割・職務の見直し」では、従来の職務をそのまま継続させるのみでなく、個人の経験や強みを活かした職務への再配置や、シニア社員としての新役割を含めた人材活用の検討を行うことが必要となってきます。
中小企業で実行可能なシニア社員の必須役割例としては、「過去の管理職としての経験を活かし、新任管理職をサポートする」、「経験豊富な営業職が重要顧客対応のアドバイザーとしてサポートに回る」、「専門職が特定の技術分野を担当しながら、業務の継続性と技術伝承を支える」などが考えられるでしょう。
上記以外にも現状の社内役割・職務を分解して考えることで、シニア社員の活用分野は様々検討できるでしょう。こうしてシニア社員への役割・職務付与を行う際に、特に重要になるのは、上記の中で特に企業固有となるノウハウの伝承です。その理由は、前述の通り、これまで社内の熟練者が培ってきたノウハウを若手社員に引き継がないと、そのノウハウ・職務が失われ、場合によっては業績影響まで及ぶためです。
役割を付与する際に他に重要となるポイントは、責任範囲・業務範囲を現役世代と調整することも重要です。その理由は、いくら高齢化社会であるとはいえ、シニア社員頼りになるだけでなく、現役世代に責任を付与した上で育成・新陳代謝を行う必要があるためです。
2つ目の「対応する処遇設計の最適化」は当然必要です。役割・職務に応じ合理的な差異を設けること自体が、法的な同一労働同一賃金の視点で重要です。それは社員にとって公正な報酬体系と企業の総額人件費管理の合理性にもつながります。
3つ目の「役割別の柔軟な働き方の導入」は、短時間勤務や週休3日制、リモートワークや勤務地の選択肢の増加など多用な働き方を提示した上で、雇用継続が可能な仕組みがあると望ましいでしょう。これはシニア社員特有の健康面の差異への考慮の欠如や、働き方の選択肢の少なさから来る外部流出を阻止する目的が主な理由です。また、短時間勤務や週休3日制などは、企業として積極的な継続雇用を望まない社員への法的対応を満たしつつ、人件費抑制施策としても有効になるため検討の必要があります。勤務日数やその時間が減ることで人件費をその割合で抑制することは、当然ながら法的にも有効な対応です。 お勧め3つの他にも、人事評価によるシニア社員のモチベーション向上を始めとして様々な施策の選択肢があります。しかし、その他の選択肢は「シニア社員役割・職務の再設計」「対応する公正な処遇」「柔軟な働き方の導入」の3点を導入した後に行うべき第2、第3の矢として考えるべきです。先ずは上記のベースとなる3点の雇用ルールが確実に実行されていない環境でなければ、その他の施策は有効に働かないことが多いためです。
まとめ
日本社会の高齢化が進む中で、シニア社員の活用は企業の持続的成長に不可欠な課題となっています。労働力人口の減少が進む現状において、シニア人材の知見や経験を適切に活かすことは、企業の競争力強化にも直結します。
しかし、シニア社員活用を進めるためには、人事施策全体の見直しが必要となります。企業は、改正高年齢者雇用安定法に対応しつつ、シニア社員の役割を再定義し、適正な処遇設計や柔軟な働き方の導入を進めることが、まず中小企業が行うべきことでしょう。