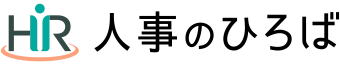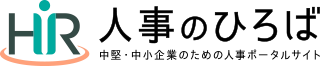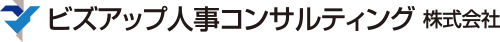近年、多様な働き方や人材の流動化が進んでおり、企業が人材マネジメントにおいて直面する課題は複雑化の一途をたどっています。そのため、従業員に対して「どのような役割を期待するか」「どのように成長を促すか」「その貢献にどう報いるか」といった問いに、組織として一貫した答えを持つことが求められてきています。そして、こうした問いに対する“設計図”となるのが人事制度であり、経営戦略と組織文化を反映した最も重要なマネジメントツールの一つと考えています。
この人事制度にはいくつかの種類と基盤となる考え方が存在しているため、本コラムでは日本で用いられ易い人事制度の種類と考え方を紹介します。
人事制度の種類
一口に人事制度といっても、その設計思想は企業の価値観や目指す姿によって大きく異なるものです。それを『自社ならではの人事制度』と位置づける事例が多く見受けられますが、基本となる人事制度の枠組み(人事制度の種類)を使用しない完全オリジナルな制度とするケースはまれであり、基本となる枠組みに自社の思想を組み込んで、自社ならではの人事制度とすることが多いのが実態です。この基本となる人事制度の枠組みには、職能資格制度、役割等級制度、ミッショングレード、ジョブ型人事制度と称されるものです。これらの違いは単なる呼称の違いではなく、「何をどの程度遂行し、何を評価し、何を処遇と結びつけたいのか」という考え方が異なります。
ここからは先述した基本となる人事制度の種類の概要を紹介します。
職能資格制度
職能資格制度は、高度経済成長期に日本企業で広く採用された制度であり、従業員の保有する能力や経験年数をベースに昇進や昇給が決まるもので、育成や長期雇用と相性が良く、一部の業種や職種においてはいまだに一定の合理性があると言われています。
役割等級制度・ミッショングレード
役割等級制度やミッショングレードは、「いま、その人が担っている役割の重さ」や「与えられたミッションの難易度・重要性」に応じて処遇を決めるもので、組織の変化に合わせて柔軟に役割が変わる企業には、適しているといわれています。
ジョブ型人事制度
ジョブ型人事制度は、欧米を中心に広がってきた思想で、「職務ありき」「職務に人をつける」考え方がベースとなるものです。各職務に対する責任範囲や期待成果を明文化し、その職務に対して必要なスキル・経験を持つ人材をマッチングさせる考え方です。属人性が低く、評価の透明性が高いというメリットがある反面、日本企業のように人が業務に合わせて柔軟に動く文化とは、相性が悪いとされています。
すべてに共通して言えることは、「組織の中で人に何を期待し、どのように応えてもらいたいか」を形にするものということです。さらに理解を深めるために、先述の種類別の考え方が「等級」「評価」「賃金」という人事主要三制度に当てはめるとどう違うのかを紹介します。
人事制度の種類に対応した等級制度の考え方
等級制度は、組織の中で社員をどう位置づけるかを定めるものです。そのため、人事制度の種類によっては、等級制度で表現される内容が異なるものとなります。
まず職能資格制度の考え方を基準として定める等級制度は、「この仕事にはこの程度の能力が必要である」といった“保有能力”や“勤続年数”に焦点を当てて組まれます。保有する能力や勤続年数は程度の違いはあれども、経過に伴い上昇するものであると考えられるため、職能資格制度の考え方を基準とした等級制度は、長期勤続奨励型や年功序列型傾向が見受けられる仕組みになることが予想されます。
次に、役割を基準とした等級制度は、「今、どんな役割を担っているか」という“期待される価値”が設計の軸になります。そのため、役割が変われば等級も変わる、という発想で制度設計や制度運用を行うことになります。 そして、ジョブ型人事制度の場合には、そもそも等級という枠組み自体がないか、あるいは職務グレードに相当するものとして存在することが推察されます。社員がどこにどう分類されるかは、その職務記述書(ジョブディスクリプション)によって定義されているため、非常に合理的である一方、柔軟な配置転換やOJTとの両立には課題があると言われています。
人事制度の種類に対応した賃金制度の考え方
等級制度が人材をどう“分類”するかの仕組みだとすれば、賃金制度はその分類に対して“どう報いるか”の考え方を示すものです。ここでも制度によって重視される観点が異なるため、以下に紹介します。
職能資格制度を基準とした賃金制度には年功的要素が多分に含まれていると言われており、例えば、年齢の上昇に伴い昇給する年齢給や、評価結果が悪くとも減額昇給は行わない、といった、年功や在籍報奨の仕組みが採用されています。また、一定期間の在籍や研修受講などが昇格・昇給の前提となることも多くあります。これは「会社に在籍して一定程度業務に携わっていれば報われる」一方で、「頑張って成果を出している人は報われづらい」という側面も持ち合わせています。そのため、成果を出している社員のモチベーション低下を招く可能性が問題視されています。
一方の役割等級制度やミッショングレード型の賃金制度では、賃金レンジが等級に連動しており、その役割の重さに応じて報酬も変動する仕組みと言われています。つまり、より高い責任や成果を求められる立場になれば、それに見合う対価が得られるという明快なメッセージが発信できることになります。年齢や勤続年数よりも、「組織にどれだけの価値を生み出しているか」が報奨される仕組みと見ることが出来ます。 そしてジョブ型を基準とした賃金制度では、職務そのものに価格が設定されているため、「誰がやるか」ではなく「何の仕事か」が基準になります。例えば、同じ営業職でも、A社の営業職とB社の営業職では職務範囲や求められる成果が異なれば、賃金も変わるということになります。この職務基準の考え方は透明性が高く、外部労働市場との整合性も取りやすい一方で、属人的な努力や貢献が処遇に反映されづらいと感じる社員も出ることが予想されます。
人事制度の種類に対応した評価制度の考え方
続いて、評価制度についても考えてみます。評価とは単なる査定や点数付けではなく、組織として「どんな行動を重視し、どういう成果を評価するか」を社員に伝えるメッセージです。そのため、人事制度の種類が変わればそれに伴って評価項目や評価軸も変わる、ということになります。
職能資格制度を基準とした評価制度では、能力や知識の向上、仕事への姿勢といった“プロセス評価”が中心となります。これは社員の成長促進には有効ですが、成果との結びつきが弱いため、スピード感を求める環境では物足りなさを感じることもあり、実際に高い成果を挙げる社員からは不満が出ることもあり得ます。
役割を基準とした評価制度では、役割に対する成果責任が明確であるため、“目標達成度”や“ミッションの完遂度”が重要な評価基準になります。その中で、一定程度プロセスの視点も組み合わせることが一般的に採られる方法で、プロセスと成果のバランスをとりながら、個人と組織の成長を連動させる設計が可能と言われています。 そして、ジョブ型人事制度における評価制度では、職務記述書に記された要件を満たしているかが判断軸になるため、“期待成果の実現”がすべてであり、プロセスよりもアウトプットそのものが問われれます。そのため、公平性は高いが、フィードバックや育成の文脈は制度とは切り離して設計する必要があると考えます。
まとめ
これらの違いを踏まえたうえで、自社はどのような性質の人事制度とすべきなのでしょうか。結論から言いますと、自社のビジネスモデル、成長戦略、そして組織文化や人材のタイプに応じて、「何を実現したいか」から逆算して制度を設計すべきである、と考えます。
例えば、ベンチャー企業であればスピード感と成果主義が重視されるため、役割やジョブベースの考え方がフィットしやすいです。一方で、新卒中心の大量採用や長期的育成を前提とする企業では、職能資格制度が今なお有効である場合もあります。どの制度にもメリットとデメリットがトレードオフであり、それを理解した上で運用・改善していくことが、人事制度を活かすカギとなります。
人事制度とは、仕組みそのものではなく、「どう使い、どう伝え、どう育てるか」によって意味を持つもので、経営の意思と組織の価値観が反映されてこそ、従業員の納得感を生み出し、企業の成長を支える土台になるのではないでしょうか。 本コラムが皆様の企業における人事制度設計の一助になると幸いです。