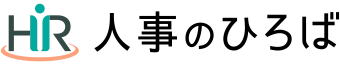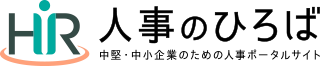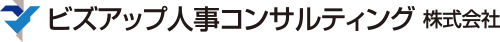はじめに
管理職や指導職が部下に対して行う評価は、組織の成長と社員のモチベーション向上に大きな影響を与えるため、公正性や納得感を伴うことが求められます。しかし、評価者自身が評価の方法や基準を理解しておらず、適切な評価とフィードバックができていないというケースも少なくありません。
そのため、管理職・指導職を対象に評価者としてのスキルを身につける学習の場として、「評価者研修」を実施する企業が増加しています。ただし、評価者研修を実施するだけで満足してしまい、時間やお金を掛けたにも拘らず、結局期待する成果を得ることができなかったという事例が散見されます。 このコラムでは評価者研修の実施を検討されている企業様に向けて、評価者研修を行う目的や、実際に行うカリキュラム(座学・演習)のテーマとして多く見られる、評価者が評価を行う際に気をつけるべきポイント(評価の対象となる行動や成果の基準)、部下が目標設定を行う際の評価者としての関わり方について解説します。
評価者研修の必要性と目的
(1)なぜ評価者研修が必要であるのか
多くの企業では人事評価制度を導入していますが、評価者のスキルや意識が不十分であると、以下のような問題が発生する可能性があります。
- 評価の公平性・納得感が低下する
- 評価者ごとに評価の対象とする行動や成果の基準が異なり、評価の納得性が生まれにくい。
- 「甘い評価をする上司」と「厳しく評価する上司」が存在し、公平性に欠ける事で従業員の不満につながる。
- 部下の成長支援が不十分になる
- 評価が単なるランク付けに終わり、評価の根拠の伝達や今後の成長に向けた目標設定の助言といったフィードバックが適切に行われない。
- 部下の成長機会を見逃すことで、組織の成長にも影響を及ぼす。
- 従業員エンゲージメントの低下
- 評価の納得性がなく、成長の機会が失われていると感じる従業員の離職率が高まる。
- 評価の基準があいまいで社員ごとに評価結果の納得感にばらつきがあると、社員同士の対立に繋がる。
このような課題を解決するため、評価者研修を実施し、管理職の評価スキルを向上させることが求められます。
(2)評価者研修の目的
評価者研修の目的は、管理職やリーダーが適切に部下を評価し、公正かつ納得感のある評価プロセスを確立することです。具体的には以下の点を重視します。
- 企業の人事評価制度の理解と適切な運用
- 評価に対する認識の統一
- 公平で客観的な評価を行うスキルの向上
- 部下の成長を促すフィードバックの習得
- 組織の目標との整合性が取れた部下の目標設定の承認
評価が恣意的にならないようにするためには、評価者自身が自社における評価制度の内容を正しく理解し、評価基準に沿って主観的にならない評価を行うことが重要です。そして、部下が評価を受け入れやすいよう、明確な根拠に基づいたフィードバックを行う必要があります。
また自社の人事評価制度に、自身の設定した目標に対する達成度合いを評価する項目がある場合、評価者の役割は、部下が設定した目標の内容が適切であるかを判断し、必要に応じて助言を行って内容を修正させることも含まれます。 上記の内容を踏まえ、評価者研修を実施する際には、以下のカリキュラムで実施される事例が多く見られます。
- 自社の評価制度の概要説明 ⇒自社の評価制度が変更となった場合は必須。
制度の変更がなくとも、改めて内容を理解し、これまでのやり方が基準に合っているものであったかを確認する機会として実施する企業が多い。「誰が誰を(評価者と被評価者の関係)」「何を基準に(評価項目)」「どの様に(評価結果の算定方法・基準)」評価するのかが明確となるように説明することが求められる。 - 評価者としての在り方・評価を行う際のポイントについての説明⇒評価者に対して、そもそもどういった目的で人事評価を行うのか、評価者としてあるべき姿とは何かといった前提の共有や、実際に人事評価を行う場合にどういった点に注意する必要があるかといった実践的な内容について説明します。評価を実施する際のポイントなどは、座学だけでなく実践的な演習を行うと、参加者も能動的になり、深い理解に繋がります。
- 部下の設定した目標の適切化
⇒昨今は、自身の設定した目標への達成度合いを評価項目とする企業が増えております。しかし、設定した目標が会社や所属している組織の業績に繋がらない内容となっていては、目標を達成しても意味がありません。評価者は、部下の設定した目標が下記の視点を踏まえた内容となっているか確認し、必要に応じて修正に向けたアドバイスを行います。
- 個別の目標内容が組織目標(業績指標)と連動しているか
- 目標の難易度が被評価者に対して適切な水準となっているか
- 評価の段階を設定できる具体的かつ定量的な内容となっているか
評価者研修では、座学で上記のような目標設定のポイントを学習した後、参加者が目標設定者と目標承認者に分かれ、それぞれが設定した目標の内容をフィードバックする実践的演習を行うといった事例が多く見られます。
評価者研修の議題例の紹介
前章で紹介したように、評価者研修では、期中・期末において実際の評価を行う際の注意点・ポイントを理解し、期首における目標設定の内容を承認するための視点を習得することが主眼に置きます。この章では、評価者研修を行う際によく取り上げられる議題として、評価を行う際の注意点・ポイントや、目標設定を行う際の基準について紹介します。
(1)評価を行う際の注意点・ポイント
①評価エラーの原因となりやすいバイアスの内容を把握する
評価には様々なバイアス(認知の歪み)が入り込むことで、エラーが発生する可能性があります。代表的なバイアスとして以下のようなものが挙げられます。
- ハロー効果
特定の優れた(または劣った)側面が、他の評価項目にも影響を与える - 寛大化・厳格化傾向
評価者の性格によって評価が甘くなったり厳しくなったりする - 期末効果
直近の業績や行動だけを評価に反映させてしまう - 対比誤差
評価者が被評価者を評価する場合、評価者が自分自身や他の被評価者を基準にして評価することで、主観的な評価をしてしまう
バイアスの影響を最小限にするために、評価者は意識的に客観的な視点を持ち、複数の評価者と連携することが求められます。
②行動に基づく評価を心がける
期中において重要となるのは、人事評価期間内での日頃の業務に対して、人事評価を意識して行動内容に注目しながら、部下を良く観察することです。一定の評価期間が終了した後にまとめて評点やコメントを残すことは、人事評価期間のズレや不確実な記憶に基づく人事評価になりやすく、納得性の高い人事評価とは言えません。期中の間に観察された行動が、評価の対象となる内容(職務遂行行動)であったか、制度で定められたどの評価要素に該当するかを記録しながら、評価結果を検討する際の参考とすることが求められます。期中の行動観察は、行動の事実の内容と関連する評価要素をリアルタイムに記録していくために「行動記録ノート」を準備して活用していくことをお勧めします。
(2)部下の目標設定をサポートする際の視点と関わり方
①SMARTの原則に基づく目標設定
部下が適切な目標を設定できるよう、評価者は「SMARTの原則」を活用することが有効です。設定された目標を承認する段階では、下記の基準をもとに不足している内容がないかを確認してフィードバックを実施します。
- Specific(具体的)
目標を明確にする - Measurable(測定可能)
成果が数値化できるものにする - Achievable(達成可能)
適切な難易度で設定する - Relevant(関連性がある)
会社の方針や個人のキャリアに合致している - Time-bound(期限がある)
期限を設定する
また、目標の内容が外部要因も含めた結果でなく、自身の行動によって結果が出る内容であるかも重要な視点となります。例えば、IT系の技術部門のチームリーダーが、「自チームにおける○○資格の取得者を半期中に△人達成する」という目標を立てた場合、実際に自身の行動で100%達成できる目標にはなっておらず、最終的な結果はチーム内のメンバーの努力に委ねられるため、目標を立てた評価対象者自身の貢献度が曖昧になります。この場合は、「メンバーが○○資格を取得するために、月□回の勉強会を開催する」といった方が、適切な内容となります。
②目標達成の進捗確認とフォローアップ
目標を設定した後、時期を設定して達成度合いの確認を行います。進捗が芳しくない状況であればその原因を把握し、達成に向けたプロセスを提示しつつ、必要に応じて目標の修正を行う場合もあります。部下がどのように目標達成に向けて取り組んでいるかを定期的に確認し、必要に応じてアドバイスを行うべきです。
まとめ
評価者が適切な評価を行うためには、評価基準の理解、バイアスの排除、行動プロセスの重視、フィードバックの質の向上が求められます。また、部下の目標設定を支援し、継続的なフォローを行うことで、組織の成長を促進できます。
上記に記載したような、評価者に必要な知識やスキルを習得するための方法として、評価者研修を実施する企業が増えています。ただし、参加者が研修後にどういった知識やスキルを身につけてほしいのかといった理想像が描けておらず、目的なく研修を行うことは、貴重な時間とお金を浪費することで却ってマイナスとなります。
実りある評価者研修を行うために、本コラムの内容を参考にしていただければ幸いです。