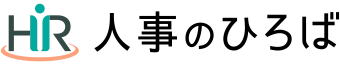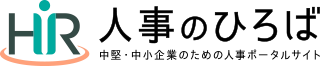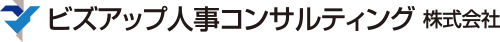1.賃金体系の決定
例えば従来は基本給を年齢給と能力給とで構成していたものを見直し、年齢給を廃止し基本給を一本化したうえで、住宅手当は廃止する、といった賃金を構成する要素を決めていくことです。
基本給に対する考え方、諸手当の存続、廃止、新設などを決定します。
この両方の視点に合致した賃金制度とは、仕事を中心に据えた賃金体系を構築するということです。ここでいう仕事中心とは、担当している職務、担っている役割、挙げている成果、会社への貢献といったものです。
これらの要素を、諸手当(インセンティブを含む)、基本給、賞与、退職金に割り当てていくことになります。
また、全社員を一律に扱うのではなく、優秀な社員には手厚く、そうでない社員にはそれなりに、とメリハリを付けた体系を作ることが重要です。
これによって、総額人件費コントロールと高い賃金水準の両立を図ることを目指します。
2.諸手当の決定
月例給を構成する要素は、基本給と諸手当に大別されます。月例給の多くの部分を基本給が占めているにもかかわらず、なぜ基本給の設計を先に行わないのでしょうか。
その理由は、賃金設計を最短コースで行うためです。つまり、諸手当を決め、月例給総額を決め、その差し引きで基本給部分を決める方法が最も効率的なのです。
3.モデル賃金の作成
モデル賃金とは、弊社で部長まで昇進する社員の月例給、年収をどの程度にするか、主任で定年を迎える社員の月例給、年収をどの程度に設定するか、ということを検討するためのものです。ここで、諸手当、月例給、賞与の金額をおおむね決定すると、基本給をどの程度の水準にしたら良いかという目安ができます。
4.基本給表の作成
ここまでくると、ようやく賃金の本丸ともいうべき基本給表の作成に着手することができ、次のステップとして等級別の基本給範囲、人事評価結果別の昇給金額を決定していきます。
5.新制度への移行シミュレーション
このようにして月例給体系ができ上がったら、新制度への移行シミュレーションを行います。
ここで、現在の基本給が新基本給で設定した範囲に収まるかどうかの確認を行い、多くの社員が収まらないようであれば、基本給表の見直しを行います。これらのステップを経て、月例給の体系を確定します。