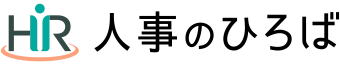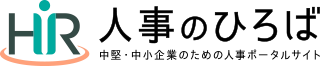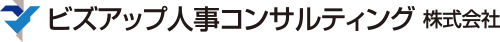ゾーン型賃金表を作成する際は、最初にゾーンの数をいくつ設定するかを検討します。ゾーンを複数設定する理由は、各等級の中でも賃金の水準に応じて、昇給額を変えるためです。これにより、同じ等級内でも賃金水準が低めの社員は多く昇給を行い、その等級の中間賃金に近づけていきます。
一方、すでに高めの賃金水準になっている社員は、昇給幅を少なめにするというきめ細かな設定が可能となります。
1.ゾーン数の調整方法
ゾーンの数を多くすればするだけ、昇給にメリハリを付けやすくなりますが、社員個別のゾーン判定や昇給額を決める際には煩雑な事務作業が発生します。中堅企業クラスやシステム対応が可能な企業は、ゾーン数を4つ程度設定することが理想的ですが、中小企業では前ページで示した2ゾーン型をお勧めします。さらに、運用上の負担を極力軽減したい場合は、シングルゾーン型でも良いと考えます。
2.基本給範囲の決め方
ゾーンの数をいくつ設定するかを決めたら、次に等級ごとの基本給範囲をどのように設定するかを検討します。その考え方には2つの選択肢があります。各等級の始点となる賃金から範囲を決定する方式、そしてもうひとつは各等級の中間賃金から始点、終点を決める方式です。始点方式では、作成したモデル賃金のうち理想モデルをベースにします。
3.ゾーン1の賃金範囲の決め方
シングルゾーン型、2ゾーン型の賃金表を選択した場合は、始点賃金方式を採用するのが望ましいと言えます。
まずは、作成したモデル賃金の理想モデルをベースに、各等級の始点賃金を決定します。各等級の始点賃金を決定したら、理想昇格年数から何年遅れの社員まで標準昇給を適用するかを決めていきます。例えば、理想年数より3年遅れの社員までを通常昇給の対象にする、5年遅れまでを通常昇給の対象にするなどです。
その年数を決めたら、標準昇給の対象であるB評価の昇給額×(理想年数+遅れ許容年数)の額を始点賃金に加算します。その金額は2ゾーン型であれば、ゾーン1の終点金額となり、シングルゾーン型であれば、ゾーンそのものの終点となります。
4.ゾーン2の賃金範囲の決め方
2ゾーン型の場合は、続けてゾーン2の終点を決めます。一般的にゾーン2は、昇給を2分の1程度に抑制して、上位等級への昇格意欲を高めることを目的に設定します。通常昇給適用期間終了後、あと何年昇給を許容するかという視点で範囲を決定します。例えば3年であれば、通常昇給のB評価の半額×3年の金額をゾーン1の終点(ゾーン2の始点)に加算することになります。
ゾーン1、ゾーン2の許容年数を長くすればするほど、各等級の賃金レンジが広くなり、上位等級の賃金範囲との重複が多くなります。
ただし、賃金制度としては、年功的になりがちですので、許容年数の考え方には注意が必要です。